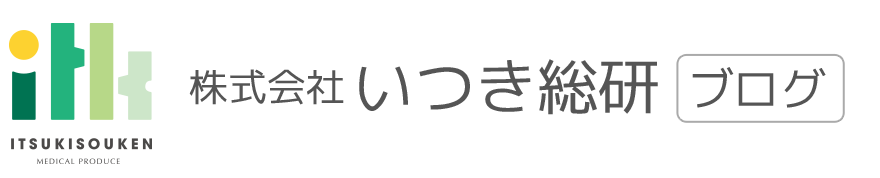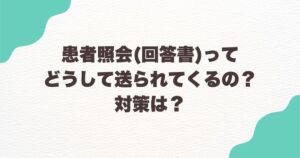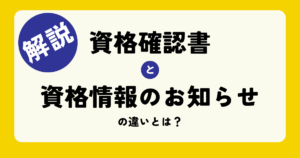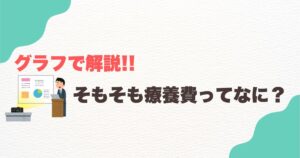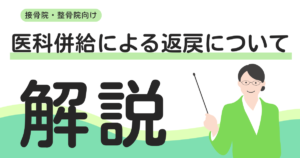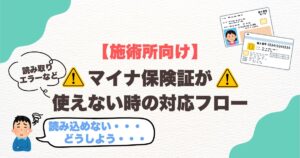接骨院・整骨院における不正請求とは

皆さんこんにちは!いつき総研のばーやんです!
接骨院・整骨院では、健康保険を利用した「受領委任払い制度」によって、患者さんが少ない自己負担で施術を受けられる仕組みがあります。
しかし、この制度を巡って問題となっているのが「不正請求」です。
意図的なのか、もしくは気づかぬうちに制度を逸脱した請求をしてしまうと、行政処分や患者さんからの信用を失う可能性があります。
今回はどのようなものが不正請求になるのか、どう防止するべきかを解説していきます。
最後まで見ていただけると嬉しいです!
不正請求とは?
不正請求とは、受領委任払い制度を悪用して、実際の施術内容以上に療養費を請求する行為を指します。
例えば捻挫や打撲など、健康保険の対象になる外傷に対する施術であれば保険適用が可能ですが、これを偽装して本来保険が適用されない施術にまで請求を行うと、それは不正となります。
このような行為は健康保険法に違反するもので、最悪の場合は
- 受領委任払いの契約打ち切り
- 業務停止命令
- 柔道整復師免許の取消
といった厳しい行政処分につながります。
接骨院・整骨院で多い不正請求の手口
部位転がし
患者の負傷部位を次々に変えて、通院を長引かせる手口です。本来であれば治癒している部位を別の部位にすり替え、継続して療養費請求する。
施術箇所の偽造
実際に施術を行っていない部位をレセプト上に記載することです。
例:肩の施術をしたのに、腰の施術として請求する。
来院日数の水増し(過剰請求)
実際に来院していないのにレセプト上に記載することです。
例:月に5日しか来院していないのに10日来院したことにして請求する。
施術部位の水増し(過剰請求)
1部位の治療で済む内容に、無関係な部位を加えて複数部位で請求する行為です。必要以上の療養費を得るための不正です。
受傷理由の改ざん
保険適用されない慢性的な痛み(例:肩こり)を、「打撲や捻挫」と偽って保険対象に見せかける行為です。
無資格者による施術の請求
柔道整復師以外のスタッフ(整体師・学生アルバイトなど)が施術したにもかかわらず、柔道整復師名義で請求するケースです。
国が実施する不正請求対策
接骨院の不正請求防止のため、国は以下のような施策を導入しています。
長期施術による減額制度
5ヶ月を超える施術には、1部位あたり75%への療養費減額措置。さらに3ヶ月を超える場合は「長期施術継続理由書」の提出が必須。
多部位請求の制限
3部位目以降の請求は60%の減額となり、4部位目以降はまとめて請求不可に。水増し防止を目的とした仕組みです。
受領委任払い制度の厳格化
2018年以降、制度を利用するには
・一定の実務経験
・施術管理者研修の受講
が必要になりました。届け出の際も、証明書類の添付が義務化されています。
不正請求を疑われないためにできる対策
不正の意図がなくても、記載ミスや認識不足で“疑われる”ことがあります。
- カルテとレセプトの整合性を保つ
- 負傷の発生機序を具体的に記載
- 3部位以上の請求時には負傷理由を明確に
- 長期施術は摘要欄に理由を記載
カルテやレセプトは、「自院の正当性を証明する書類」です。事実を丁寧に記載することで、誤解を防ぐことができます。
弊社でカルテの重要性と取り扱いについての記事もあります。
併せて見る事をお勧めします。
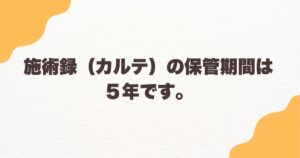
まとめ
接骨院・整骨院における不正請求は、経営にとって致命的なリスクとなりかねません。制度の理解と誠実な運用、正しい請求が何よりも大切です。
「不正のつもりはなかった」という言い訳は通用しません。
今一度、自院の療養費請求のフローを見直し、正しく保険請求を実施しましょう!